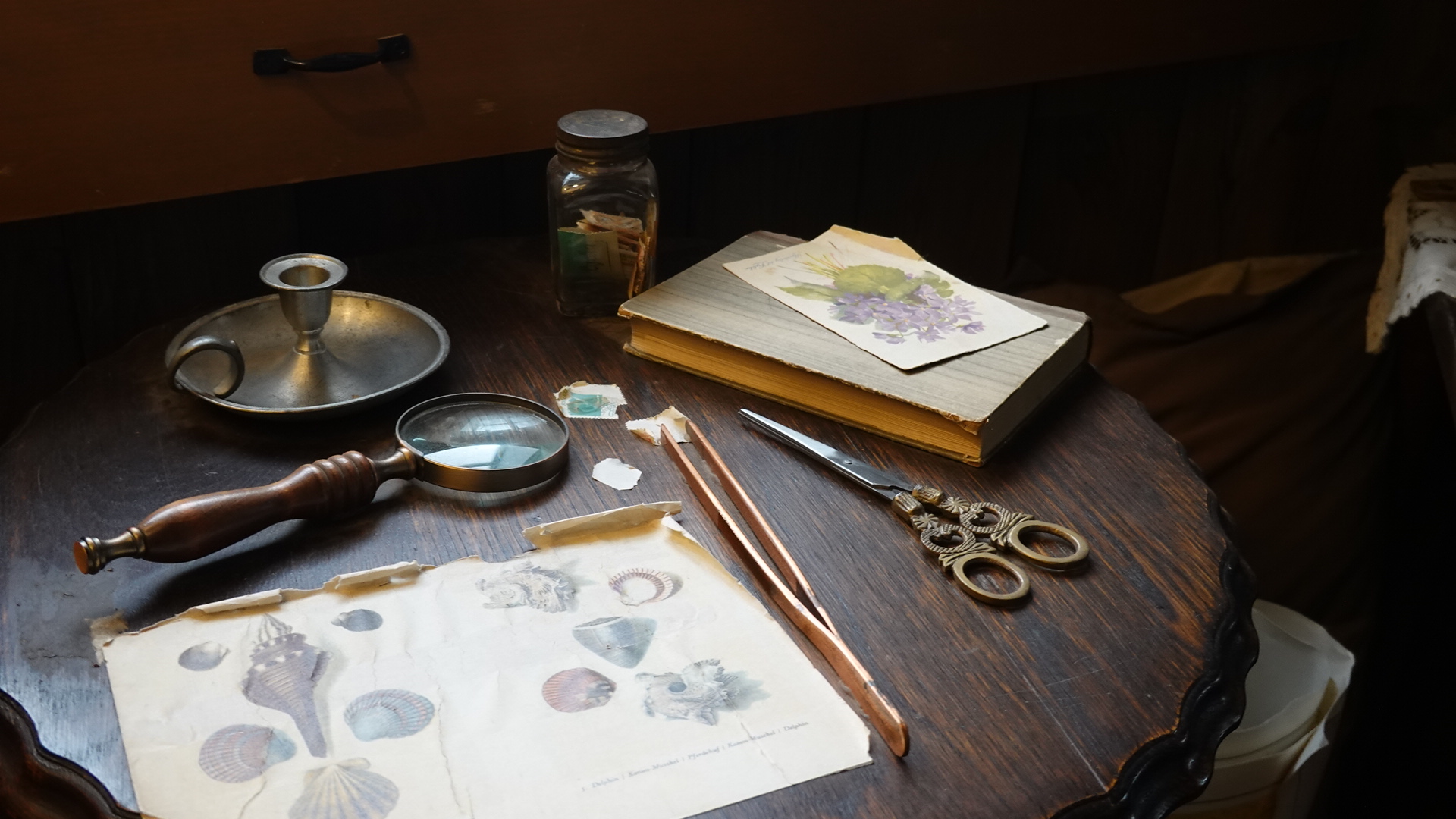1. はじめに:検温はただのルーチンじゃない
検温は毎日の業務の一部。新人の頃は「ただ体温を測るだけ」と思いがちですが、実はこの時間、患者の変化に最も早く気づける貴重なチャンスです。
ベテラン看護師たちは「体温」以上の情報を得ています。表情、呼吸、会話のトーン…。ちょっとした“違和感”が重大な異常のサインかもしれません。
2. 検温中に看護師が見ている「5つのサイン」
(1)表情の変化
患者の“いつも通り”の表情を知っていれば、「なんか違うな」とすぐ気づけます。
ある日、普段は饒舌で「エセ医療者」状態のように自己分析して話してくれる患者さんが、「なんかわからないけど…」とだけ一言。
この一言が気になって観察を続けたところ、発作性心房細動と肺炎が発覚。発熱も重なり、数日間の抗生剤・抗不整脈薬治療となりました。
その後、話す余裕が戻り、いつもの調子で話してくれるようになったことで、「あの無口はやはり異常のサインだった」と確信しました。
(2)呼吸の様子
呼吸数が微妙に多い、呼吸の仕方が浅い、SpO₂はギリギリ正常範囲だけど「なんか不自然」…そんなとき、よくよく見ると肺炎の始まりだったということも。
(3)声のトーン・話し方
「はい」の一言にも情報は詰まっています。
普段なら詳しく話してくれる患者が、急に言葉数が少なくなる。“話せない”というサインは、時に“痛み”よりも鋭い異常の現れ方なのです。
(4)体位・寝返りの仕方
動きが鈍い・姿勢がいつもと違う――これは「本人すら自覚していない不調」の兆候です。
体のだるさ、発熱、心不全の軽度増悪など、意外と“寝返り”がヒントになります。
(5)皮膚の状態や手足の冷感
検温で手を握るとき、肌のしっとり感や冷たさに気づけることがあります。
その“ちょっとした違和感”が敗血症や脱水の初期発見につながることも。
3. 実際のエピソード:違和感を見逃さなかったからこそ
前述の“エセ医療者”さんの話は、私自身にとって大きな教訓でした。
あれだけ饒舌だった人が、「なんかわからない」と一言だけ話して終わった――それは**“話す余裕すらない”状態**だったのです。
それ以降、私は後輩たちにこう伝えています:
「普段と違うと感じたら、その“違い”の正体を五感で探して、しつこく訪室して確認してほしい」と。
話すこと・黙ること、動くこと・動かないこと、そのすべてが“観察”の対象であり、看護師の判断材料なのです。
4. なぜそれが大事なのか?アセスメントにつなげる力
検温はただの数値を取る作業ではありません。「変化に気づく力」こそが、看護の核です。
新人のうちは、「そんなのわかんない…」と思うかもしれませんが、“昨日と今日の違い”を比べる習慣をもつだけで、確実に観察力は伸びます。
5. おわりに:新人にもできる観察力のコツ
- “昨日との違い”を探すこと
- いつもの○○さんと比べて変じゃないか?
- 「気になる」と思ったら、声に出すこと
小さな違和感が、大きな異常を早く見つける鍵になります。
検温というシンプルな作業のなかにこそ、看護師としての力が詰まっているのです。