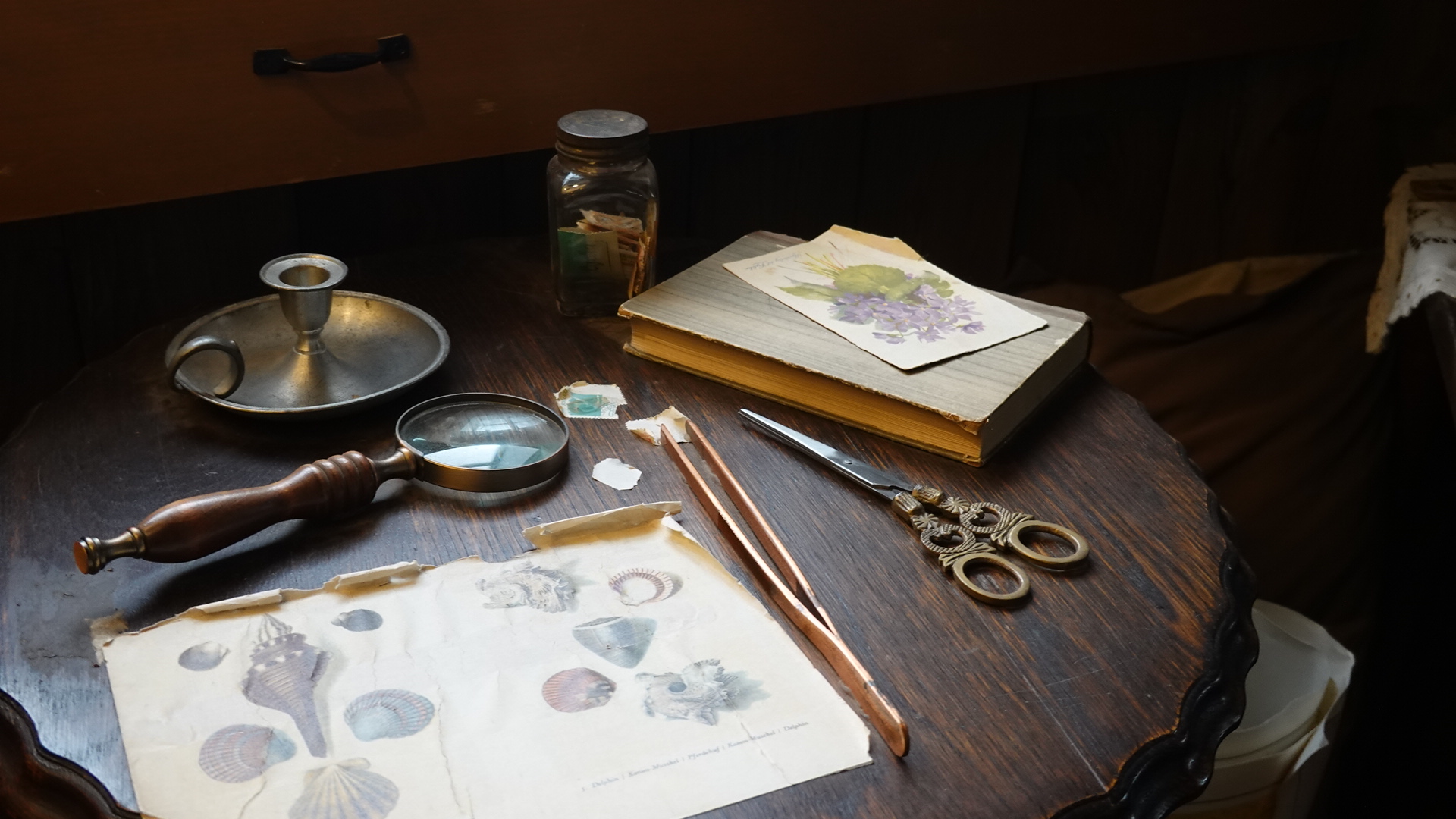こんにちは。久しぶりの更新になります。
これまでは主に「看護師の仕事内容」について書いてきましたが、今回は少し視点を変えて、私が今年から新しく任されている「委員会の委員長業務」について綴ってみたいと思います。
実は今年が初めての委員長。正直に言うと「委員会なんて月に数回の会議を回せばいい」くらいに軽く考えていました。ところが、いざやってみると想像以上に大変で、驚きの連続です。
まず、委員会は看護師だけでなく、看護補助者、事務職、リハビリスタッフ、薬剤師といった多職種で構成されています。立場や業務内容が異なるメンバーが集まるので、会議の進め方ひとつ取っても工夫が必要。私は毎回アジェンダを事前に作り、議論がスムーズに進むよう心がけています。しかし、実際に会議をすると「熱心に意見を出す人」と「できれば早く終わってほしい人」の温度差を痛感することもしばしば。議論を深めつつ、全員が置き去りにならないようにするのは、なかなか骨の折れる作業です。
さらに、委員長をやってみて初めて知ったのは「根回しの大切さ」。会議だけでは物事は決まりません。委員会外の部署に協力をお願いしたり、事前に説明して理解を得たりと、会議の前後に動く時間がむしろ多いくらいです。正直、想像以上に大変で、最初は「ここまでやるの?」と驚きました。
そして何より重く感じているのが、「問題が起きた時に、委員長が一番に動かなければならない」というプレッシャー。トラブルは待ってくれません。時に判断を迷いながらも、自分が先頭に立って動かざるを得ない場面が続くと、正直押しつぶされそうになることもあります。
そんな時に支えになっているのが、以前読んだドラッガーの『マネジメント』。難しい本ですが、「我々の事業は何か」「何であるべきか」という問いを思い出すと、委員会の目的や存在意義を見つめ直すきっかけになります。「委員会は何のためにあるのか」を考えると、自分の迷いや焦りが少し整理され、次の一歩を踏み出す勇気につながるのです。
委員長業務は確かに大変ですが、決して一人で抱えるものではないとも感じています。もし同じように委員会運営で悩んでいる方がいたら、ぜひコメントやアドバイスをいただけると嬉しいです。きっと同じ悩みを持つ人は多いはず。一緒に試行錯誤していければ心強いなと思っています。